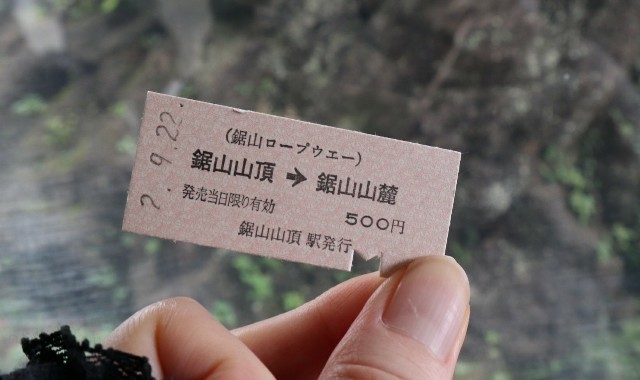ブログへお立ち寄り頂きありがとうございます。
バスに乗って一度JR京都駅へ行き、そこから市バスに乗ってバス停清水道で下車します。
このバス停では大勢の観光客が降りました。
それもそのはず、バス停は清水通りの前です。
そして大多数が清水寺へ向かって歩いて行きます。
べる家は・・・・
道路を渡って反対側へ。
息子「なんで道路を渡るの?清水寺はあっちでしょ」
べる「清水寺には行かない」
息子「えー!!ここまで来て行かないの?」
清水寺は修学旅行で行ってるでしょ。
べるは7回行ってるしね。
でも、よく考えたら家族で行った事は一度もありませんでした(^-^;そのうちね~。
冥界へ通じる六道珍皇寺
実(げ)に恐ろしやこの道は 冥途に通ふなるものを
心ぼそ鳥辺山 煙の末もうす霞む・・・

※画像はお借りしています
京都では「六道さん」の名前で親しまれ、お盆の精霊迎えに参拝する有名なお寺です。
本堂
べるは中に入ったんですけど、ちょっと写真を撮るは遠慮してしまいました。
※画像はお借りしています
本殿前に掲げられている提灯を、モノクロ撮影してみました。
雰囲気バッチリです。
六道とは仏教で、地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人道、天道という6つの冥界を指し、人は因果応報によって輪廻転生をする
と言われています。 昔は道が交わる場所を辻と言い、6つの道が交わるこの場所はあの世とこの世の境目で、六道の辻と呼ばれました。

あの世まで響く鐘もあります。
珍皇寺と縁の深い小野篁
貴族であった小野篁は小野小町の子孫で、二条城の北に住まいがあり、政府の役人して嵯峨天皇に仕えていました。
夜は珍皇寺までやってきて、ここの井戸を通って冥界へ行って閻魔大王の高官として働いていた言われています。
井戸は普段非公開ですが、格子の隙間から覗き見る事ができます。
▼冥界へ通じる井戸
※画像はお借りしています
▼冥界から帰って来る時の黄泉がえりの井戸
※画像はお借りしています
閻魔様の前に引き出された時に、篁のとりなしで生き返ったという蘇り伝説があります。
本尊、篁作の閻魔大王像、井戸等は普段は非公開ですが、特別拝観の時にいけば見る事が出来そうです。
お岩大明神
境内の一角にたくさんのお地蔵さまがあって、水子を供養しています。
その側にお岩大明神がありました。
夫婦円満の神として信仰されていたようです。
髑髏町
昔は今と違って亡骸を火葬する習慣がありませんでした。
貴族は土葬、身分の低い物は風葬といって、いわゆる放置、又は山の下に埋葬されて無縁仏扱いでした。
珍皇寺がある辺りは、そこかしこに髑髏が転がっている、、、なので髑髏町と呼ばれていました。
江戸時代になると町名が不吉だと、轆轤町(ろくろちょう)に変更されています。
御朱印
本堂の中で住職に書いて頂きました。
行事のある時は限定御朱印が多数あります。
金泥の御朱印はここが始まりだと思います。
アクセス
時間が無くて行けなったんですが、近くにみなとや幽霊子育て飴本舗があります。